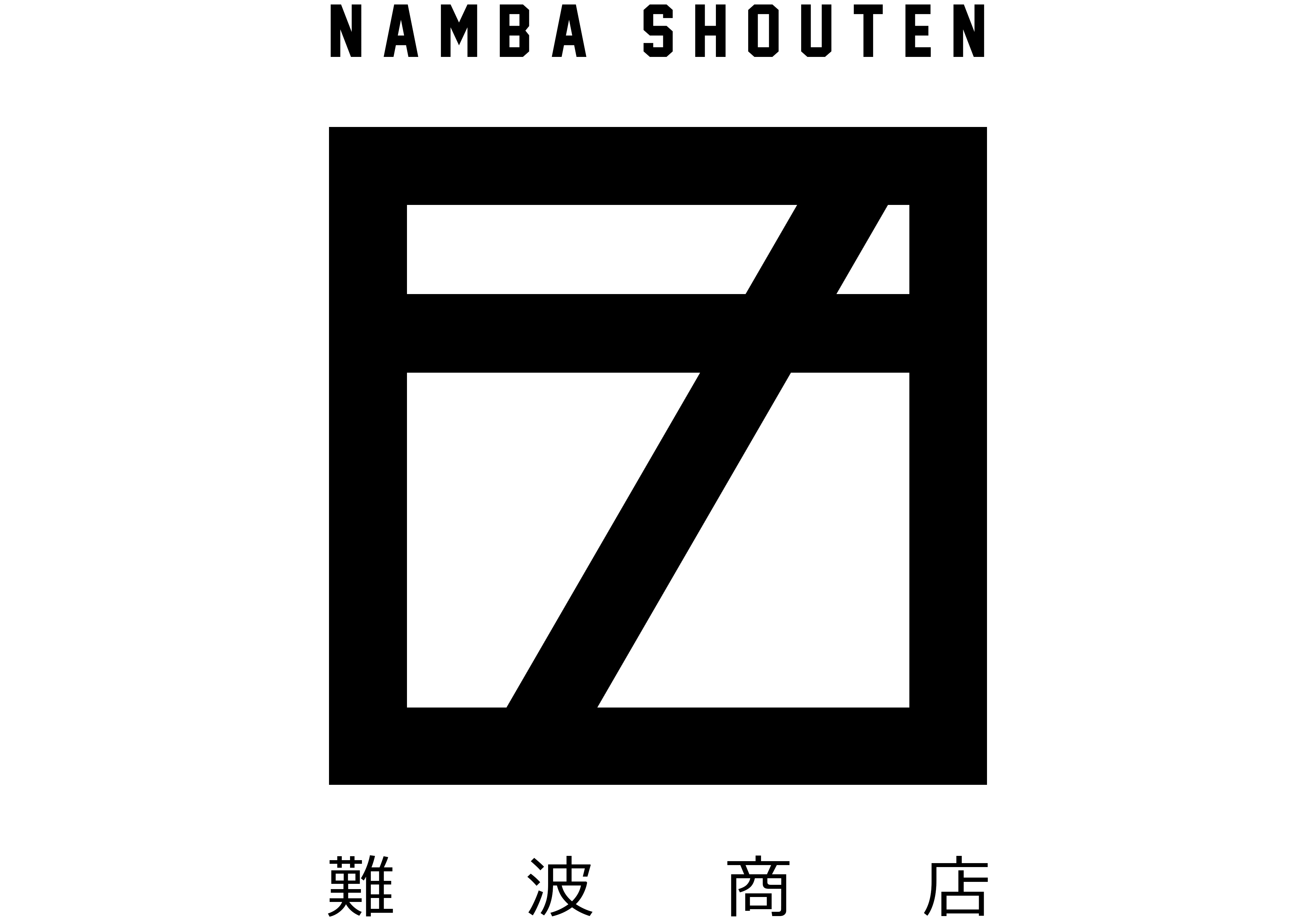2025/07/26 16:07


「馬乗り袴(うまのりばかま)」と聞いて、どんな姿を思い浮かべるでしょうか。
裾が大きく広がり、風をはらんでゆったりと揺れる──そんな印象を持つ方もいるかもしれません。実際、それは動きやすさを重視して考え抜かれたデザインなのです。
もともと馬乗り袴は、文字通り馬に乗るために考案された袴で、戦国時代の武士たちに愛用されていました。特徴的なのは、股の部分が分かれた構造になっている点。これによって足さばきが自由になり、作業や戦闘、儀式の際にも着用しやすいという利点がありました。
時代が下ると、その実用性は農民や職人の衣服としても活かされていきます。特に、大正から昭和初期にかけては、麻素材の馬乗り袴が夏の作業着として広く普及しました。通気性が良く、汗をよく吸い、洗ってもすぐ乾く──理にかなった日常着だったのです。
今回ご紹介する一着も、そんな時代背景の中で使われていた馬乗り袴。麻に藍染を施した布地は、今では出会うことも難しい貴重な古布です。実際に着用され、洗われ、補修されながら、日々の生活の中で育ってきた布は、新品の生地にはない味わいと深みを湛えています。
近年、このようなヴィンテージファブリックは、日本国内だけでなく海外でも高い評価を得ています。特に欧米のアーティストやデザイナーの間では、「Wabi-Sabi」や「Boro」といった日本独自の美意識と重ねられ、アート作品やリメイクファッションに活かされるケースも増えてきました。
布そのものが語りかけてくるような魅力を持つ馬乗り袴は、ただの衣服ではありません。そこには暮らしの工夫、自然との関わり、そして手を動かして布を大切に扱ってきた人々の痕跡があります。
私たちは、そんな一着に今ふたたび出会い、触れ、感じることができるのです。
この袴を通して、あなたも小さな時間旅行をしてみませんか?
リメイクして新たな命を吹き込むもよし、そのまま飾って生活空間に静かな存在感を加えるもよし。
古き布に、いまの自分の感性を重ねる──そんな楽しみ方をぜひ味わってみてください。
↓Click↓